2018年10月12日
経費
お金の話
この技術研究会を開催するとしていくらくらいかかるんでしょうか?
1)会場費
2)印刷費(配布資料、案内看板)
3)工具・材料費
4)その他
九工大で行なっている機械・工作技術セミナーの予算は5万円(2017)、7万円(2018)です。
そのうちマイスター招聘費が2万円(2017/1名)、4万円(2018/2名)となっています。
工具・材料費が2万円、その他消耗品などに1万円となっています。
どう言った講習内容にするかで増減はあると思います。
各地でマイスター講習は難しいので他の形になると思います。
そうなるとマイスター招聘費は必要なくなります。それに伴い工具・材料費も不要となります。
見えない形での消耗品や備品・設備の持ち出しもありますが、実質1万円から2万円程度で開催できるのではと考えています。
これらの経費は、参加者一人あたり500〜1000円程度の参加費を負担してもらえば賄えると思います。
お金はいくらでもかけられるでしょうが、最低限にする方法もあるのではと考えています。
例えば、
印刷費の削減のため、資料はウェブ上に置いて各自でダウンロードしてもらい、必要な人は印刷してもらう。
名札ケースや看板の使い回し。初年度に準備したものを数年使い続ける。
などなど。。。
この技術研究会を開催するとしていくらくらいかかるんでしょうか?
1)会場費
2)印刷費(配布資料、案内看板)
3)工具・材料費
4)その他
九工大で行なっている機械・工作技術セミナーの予算は5万円(2017)、7万円(2018)です。
そのうちマイスター招聘費が2万円(2017/1名)、4万円(2018/2名)となっています。
工具・材料費が2万円、その他消耗品などに1万円となっています。
どう言った講習内容にするかで増減はあると思います。
各地でマイスター講習は難しいので他の形になると思います。
そうなるとマイスター招聘費は必要なくなります。それに伴い工具・材料費も不要となります。
見えない形での消耗品や備品・設備の持ち出しもありますが、実質1万円から2万円程度で開催できるのではと考えています。
これらの経費は、参加者一人あたり500〜1000円程度の参加費を負担してもらえば賄えると思います。
お金はいくらでもかけられるでしょうが、最低限にする方法もあるのではと考えています。
例えば、
印刷費の削減のため、資料はウェブ上に置いて各自でダウンロードしてもらい、必要な人は印刷してもらう。
名札ケースや看板の使い回し。初年度に準備したものを数年使い続ける。
などなど。。。
2018年10月11日
備品
この研究会を開くにあたってどの様な用品が必要となるでしょうか。
どのような演習を行うかによって変わってくると思いますが、一般的には下記のようなものではないかと思います。
漏れなどありましたらご指摘ください。リスト化しておきたいと思います。
・受付関係
机
椅子
名札
名簿
筆記用具
・演習
ホワイトボード
PA(マイク)
プロジェクター
・交流会
PA(マイク)
・会場関係
案内看板
PA(マイク)
・配布資料
スケジュール
会場案内
名簿
名札
領収書
アンケート
どのような演習を行うかによって変わってくると思いますが、一般的には下記のようなものではないかと思います。
漏れなどありましたらご指摘ください。リスト化しておきたいと思います。
・受付関係
机
椅子
名札
名簿
筆記用具
・演習
ホワイトボード
PA(マイク)
プロジェクター
・交流会
PA(マイク)
・会場関係
案内看板
PA(マイク)
・配布資料
スケジュール
会場案内
名簿
名札
領収書
アンケート
2018年08月15日
事務局
これを書き出して想像以上に総務の業務が多いことに気がつきました。
演習とか交流会とか表の華やかな部分だけは大きく想像を膨らませることができていました。
その夢を語ることは簡単でも、実現させる具体的な手段や方法を示し理解してもらうのは大変です。
これだけのことをやろうと言うのだからそれなりの組織とそれをまとめる事務局が必要です。
現在「機械工作技術研究会連絡網」と言う緩やかなネットワークを作っています。
今は、主にメーリングリストを使っての情報交換を行っています。
メンバーは各地の技術研究会でお会いした方にこちらからお声がけさせていただいて加わっていただいています。
言い出しっぺなので、事務局は九州工業大学、事務局長は私が務める覚悟はできています。
しかしながら私にも定年がやって来ます。それまでに継続的に続けていける組織にしておかなければいけません。
将来的なことや堅苦しいことは抜きにしても、機械工作技術研究会の実現に興味のある方は、このネットワークに加わっていただければと思います。
ご連絡をお待ちしています。
機械・工作技術セミナーの2日目終了後にミーティングを開こうと思います。
興味ある方はどなたでもご参加いただけますから、都合のつく方は足をお運びください。
演習とか交流会とか表の華やかな部分だけは大きく想像を膨らませることができていました。
その夢を語ることは簡単でも、実現させる具体的な手段や方法を示し理解してもらうのは大変です。
これだけのことをやろうと言うのだからそれなりの組織とそれをまとめる事務局が必要です。
現在「機械工作技術研究会連絡網」と言う緩やかなネットワークを作っています。
今は、主にメーリングリストを使っての情報交換を行っています。
メンバーは各地の技術研究会でお会いした方にこちらからお声がけさせていただいて加わっていただいています。
言い出しっぺなので、事務局は九州工業大学、事務局長は私が務める覚悟はできています。
しかしながら私にも定年がやって来ます。それまでに継続的に続けていける組織にしておかなければいけません。
将来的なことや堅苦しいことは抜きにしても、機械工作技術研究会の実現に興味のある方は、このネットワークに加わっていただければと思います。
ご連絡をお待ちしています。
機械・工作技術セミナーの2日目終了後にミーティングを開こうと思います。
興味ある方はどなたでもご参加いただけますから、都合のつく方は足をお運びください。
2018年08月08日
スタッフ
この研究会を運営するのに何名くらいのスタッフが必要なのでしょうか。
当日に発生する業務を挙げてみると
受付(準備、業務、撤収)
演習(準備、講師、撤収)
交流会(準備、進行、撤収)
会場(準備、案内、撤収)
事前、事後の業務としては
会場の手配
備品の準備
参加登録
アンケートの集計
どれも開催校だけで負担するのではなく、参加者がスタッフとなってできることを担っていくこともできるでしょう。
皆んなで作りあげる研究会にした方が良い気もします。
開催校でなければできない業務としては、
会場の手配、備品の準備、会場案内くらいではないでしょうか。
事前事後の参加登録やアンケートの集計は事務局で行うことができます。
当日業務の机や椅子の設置、受付確認をはじめその他の業務も参加者の有志、事務局で補うことができると思います。
交流会は大学生協などを使えば、そちらにお任せできます。
手間や人数やお金は、かけようと思えばいくらでもかけられます。その分、中身も充実はしてくるでしょう。
逆にコンパクトに手間ヒマかけずに作りあげることもできるでしょう。
どちらも行き過ぎては良いものとは呼べないものになる気がします。
最低限このくらいという器を提示し、開催校それぞれの立場や環境で盛り付け、色付けをしてもらう様な方法が良いのかもしれません。
そのためにもここで言う「事務局」や「有志」と言ったものを拡充させておく必要がありますね。

当日に発生する業務を挙げてみると
受付(準備、業務、撤収)
演習(準備、講師、撤収)
交流会(準備、進行、撤収)
会場(準備、案内、撤収)
事前、事後の業務としては
会場の手配
備品の準備
参加登録
アンケートの集計
どれも開催校だけで負担するのではなく、参加者がスタッフとなってできることを担っていくこともできるでしょう。
皆んなで作りあげる研究会にした方が良い気もします。
開催校でなければできない業務としては、
会場の手配、備品の準備、会場案内くらいではないでしょうか。
事前事後の参加登録やアンケートの集計は事務局で行うことができます。
当日業務の机や椅子の設置、受付確認をはじめその他の業務も参加者の有志、事務局で補うことができると思います。
交流会は大学生協などを使えば、そちらにお任せできます。
手間や人数やお金は、かけようと思えばいくらでもかけられます。その分、中身も充実はしてくるでしょう。
逆にコンパクトに手間ヒマかけずに作りあげることもできるでしょう。
どちらも行き過ぎては良いものとは呼べないものになる気がします。
最低限このくらいという器を提示し、開催校それぞれの立場や環境で盛り付け、色付けをしてもらう様な方法が良いのかもしれません。
そのためにもここで言う「事務局」や「有志」と言ったものを拡充させておく必要がありますね。

2018年08月01日
プログラム
2日型(午後半日+午前半日)を基本に考えています。
1日型(午後半日)でも良いし、
2日型、1日型の前か後ろか前後にオプション企画を組み込むとか、
主催機関のそれぞれの裁量で良いと思います。
かと言って、あまりに自由だと全部考えないといけなくなり手間隙がかかります。
そこで、モデルプランを提示しておきます。
演習の内容もモデルを作っておいて、主催期間のやってみたいもの、実施し易いものを組み合わせて作っていただければと考えています。
演習モデルについては「演習」のカテゴリーで掲載していきます。

1日型(午後半日)でも良いし、
2日型、1日型の前か後ろか前後にオプション企画を組み込むとか、
主催機関のそれぞれの裁量で良いと思います。
かと言って、あまりに自由だと全部考えないといけなくなり手間隙がかかります。
そこで、モデルプランを提示しておきます。
1日目
13:00〜13:30 受付
13:30〜14:00 開講式
14:00〜15:30 演習1
15:30〜17:00 演習2
17:30〜19:30 交流会
2日目
09:30〜11:30 演習3
11:30〜12:00 修了式
演習の内容もモデルを作っておいて、主催期間のやってみたいもの、実施し易いものを組み合わせて作っていただければと考えています。
演習モデルについては「演習」のカテゴリーで掲載していきます。

2018年07月25日
参加者数
過去の実績を見てみると
全国規模の技術研究会で行われた工作系分科会(東京大2017、信州大2018)で70名程度、
九州地区総合技術研究会in九工大の機械工作セッション(2016)では40名、
これは大きな研究会の1つのセッションとして行われたからこんなに集まっているんだよ。と言う意見は否定できないと思います。
機械工作の単独のセミナーとして行われた九工大の機械工作技術セミナー(2016、2017)は30余名。
ガラス工作技術シンポジュームは50名近く集まっているようです。
初の単独の研究会ということで興味津々できてくれる人もいるのではないか。
初物でどんなものかと警戒して集まらないのか
これらから予想すると、
40名はいくでしょう。いってもらはないと。。。いってほしい
70名は厳しいかな。。。
多くて100名、50名はいきたいところ。
工作系の人は、この手の研究会が苦手な人(はにかみ屋?)が多い気もするので、参加するのは億劫なのかも
そんな人の持っている技術を垣間見たいんだけどなぁ。
出てこないならこちらから行く と言うことで全国各地の輪番制を実現させたいですね。
と言うことで全国各地の輪番制を実現させたいですね。

全国規模の技術研究会で行われた工作系分科会(東京大2017、信州大2018)で70名程度、
九州地区総合技術研究会in九工大の機械工作セッション(2016)では40名、
これは大きな研究会の1つのセッションとして行われたからこんなに集まっているんだよ。と言う意見は否定できないと思います。
機械工作の単独のセミナーとして行われた九工大の機械工作技術セミナー(2016、2017)は30余名。
ガラス工作技術シンポジュームは50名近く集まっているようです。
初の単独の研究会ということで興味津々できてくれる人もいるのではないか。
初物でどんなものかと警戒して集まらないのか

これらから予想すると、
40名はいくでしょう。いってもらはないと。。。いってほしい

70名は厳しいかな。。。
多くて100名、50名はいきたいところ。
工作系の人は、この手の研究会が苦手な人(はにかみ屋?)が多い気もするので、参加するのは億劫なのかも

そんな人の持っている技術を垣間見たいんだけどなぁ。
出てこないならこちらから行く
 と言うことで全国各地の輪番制を実現させたいですね。
と言うことで全国各地の輪番制を実現させたいですね。
2018年05月18日
会場
会場は輪番で各地を回ることが絶対条件です。
この研究会を開催する意義の半分はそこにあるのですから。
ウチだけで継続していくことは可能ですが、それは面白くない。
各大学などの工作室・工場を見学する。この上ない楽しみです
建物を見る、
機械を見る、
工具を見る、
キリコを見る、、、
それだけでわかることがたくさんあります。
自分たちが使えるヒントが転がっています。
自分たちの立ち位置、大学の工作室のレベルを知ることができます。
最初は、言い出しっぺのウチ「九州工業大学」でしょうね
その次と次の次(2年先)までは決めておきたいと思っています。
2020年、2021年にやっていただけるところが決まれば2019年に第1回(九工大)を開催したいと思います。
難しければ1年先伸ばしになると思います。それ以上先延ばしにすることは今のところ考えていません。
いずれにせよ時間的余裕はあまりありません。
主催校の負担をなるべく軽減するような方法で開催できればと考えています。
我こそは! と思われる方
考える余地はあるなぁ と思われた方
ご連絡お待ちしています。
色々とご相談しながら進められればと思います。
総合技術研究会、実験実習技術研究会などと合わせて全国工作室巡りをやりましょう!
スタンプ帳とかご朱印帳作りますか
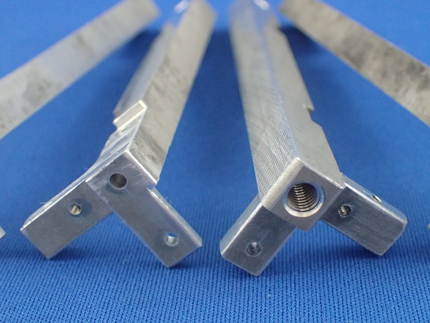
この研究会を開催する意義の半分はそこにあるのですから。
ウチだけで継続していくことは可能ですが、それは面白くない。
各大学などの工作室・工場を見学する。この上ない楽しみです

建物を見る、
機械を見る、
工具を見る、
キリコを見る、、、
それだけでわかることがたくさんあります。
自分たちが使えるヒントが転がっています。
自分たちの立ち位置、大学の工作室のレベルを知ることができます。
最初は、言い出しっぺのウチ「九州工業大学」でしょうね

その次と次の次(2年先)までは決めておきたいと思っています。
2020年、2021年にやっていただけるところが決まれば2019年に第1回(九工大)を開催したいと思います。
難しければ1年先伸ばしになると思います。それ以上先延ばしにすることは今のところ考えていません。
いずれにせよ時間的余裕はあまりありません。
主催校の負担をなるべく軽減するような方法で開催できればと考えています。
我こそは! と思われる方
考える余地はあるなぁ と思われた方
ご連絡お待ちしています。
色々とご相談しながら進められればと思います。
総合技術研究会、実験実習技術研究会などと合わせて全国工作室巡りをやりましょう!
スタンプ帳とかご朱印帳作りますか

2018年05月15日
メンバー募集
この研究会を実現させるには多くの方の協力が欠かせません。
個人や極少数で協議していると議論が行き詰まったり、視野が狭くなっていくことがあります。
そのために様々な立場や経験のある方からの意見は重要です。
・多角的な意見
・問題点の洗い出しとその解決方法
・
難しいことは抜きに、この研究会の開催に同意してくれる方が必要なのです。
でないと,
心がくじけそうになった時に立ち直れませんから
この場がそうなることが理想ではありますが、多くの人に見られることが障害になることもありますので、メールを主体に意見交換できればと思っています。
難しいことは分からんが話し相手くらいになってやろう とか
茶飲み相手でも というような軽い気持ちでご協力ください。
同意いただける方はサイドバーの「オーナーへメッセージ」で送ってください。
アドレスご存知の方は直接メールいただいても構いません。
よろしくお願いいたします。

個人や極少数で協議していると議論が行き詰まったり、視野が狭くなっていくことがあります。
そのために様々な立場や経験のある方からの意見は重要です。
・多角的な意見
・問題点の洗い出しとその解決方法
・
難しいことは抜きに、この研究会の開催に同意してくれる方が必要なのです。
でないと,
心がくじけそうになった時に立ち直れませんから

この場がそうなることが理想ではありますが、多くの人に見られることが障害になることもありますので、メールを主体に意見交換できればと思っています。
難しいことは分からんが話し相手くらいになってやろう とか
茶飲み相手でも というような軽い気持ちでご協力ください。
同意いただける方はサイドバーの「オーナーへメッセージ」で送ってください。
アドレスご存知の方は直接メールいただいても構いません。
よろしくお願いいたします。
2018年05月01日
名称
さて、ボチボチと動き出します。
まずは、この会の名称をどうしようかと考えております。
第1案としては仮称としている
「機械工作技術研究会」
工作だけだと電子工作というのもあるので機械を付けることにしました。
メリット)
他の研究会と同様でイメージしやすい。
わかりやすい、伝わりやすい。
デメリット)
固い感じがする。
難しそうなことやっていそう。
レベルの高い感じがする。
近寄り難い。
実際の内容とギャップを感じる。
セミナーとかのイメージかな。。。
カンファレンスとかは大袈裟だな。
ミーティング、、、
日本語かな。
技術交流会くらいのイメージなんだが。
技術研修会。。。
ある程度、箔を付けた方が通りが良いのかも。
これくらい書いておけば皆さんからのご意見いただけるかな
ご意見、アイデアなどお気軽にお寄せください。
まずは、この会の名称をどうしようかと考えております。
第1案としては仮称としている
「機械工作技術研究会」
工作だけだと電子工作というのもあるので機械を付けることにしました。
メリット)
他の研究会と同様でイメージしやすい。
わかりやすい、伝わりやすい。
デメリット)
固い感じがする。
難しそうなことやっていそう。
レベルの高い感じがする。
近寄り難い。
実際の内容とギャップを感じる。
セミナーとかのイメージかな。。。
カンファレンスとかは大袈裟だな。
ミーティング、、、
日本語かな。
技術交流会くらいのイメージなんだが。
技術研修会。。。
ある程度、箔を付けた方が通りが良いのかも。
これくらい書いておけば皆さんからのご意見いただけるかな

ご意見、アイデアなどお気軽にお寄せください。


